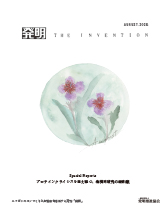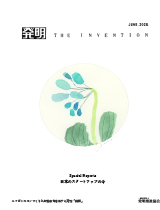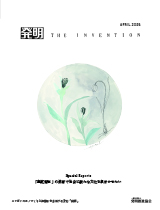|
|
|
 |
発明誌は、明治38年(1905年)創刊の「工業所有権雑誌」を前身とし、100年以上の歴史を経て今日に至っています。 特許、実用新案、意匠、商標のみならず著作権、不正競争防止法等、知的財産権全般に亘る情報を網羅し、新鮮な情報をいち早く提供しております。 発明の奨励及び知的財産権制度の啓蒙・普及の月刊誌として発明協会及び発明推進協会の会員はもとより、企業経営者、特許業務担当者、技術開発者、弁理士、学生等、幅広い読者層にご支持のもと、発行しております。 このWEB版では、雑誌で掲載された記事を公開してまいります。 (冊子版の定期購読・バックナンバーの確認方法について) 2025年12月号
2025年11月号
2025年10月号
2025年9月号
2025年8月号
2025年7月号
2025年6月号
2025年5月号
2025年4月号
2025年3月号
2025年2月号
2025年1月号
雑誌「発明」WEB版の閲覧には、FlashPlayer9以上がインストールされている必要があります。またJavascriptを有効にする必要があります。 FlashPlayerは、以下のサイトにてダウンロードいただくことが可能です。(無償) ダウンロードサイト |
|||||||||||||||||||||||||